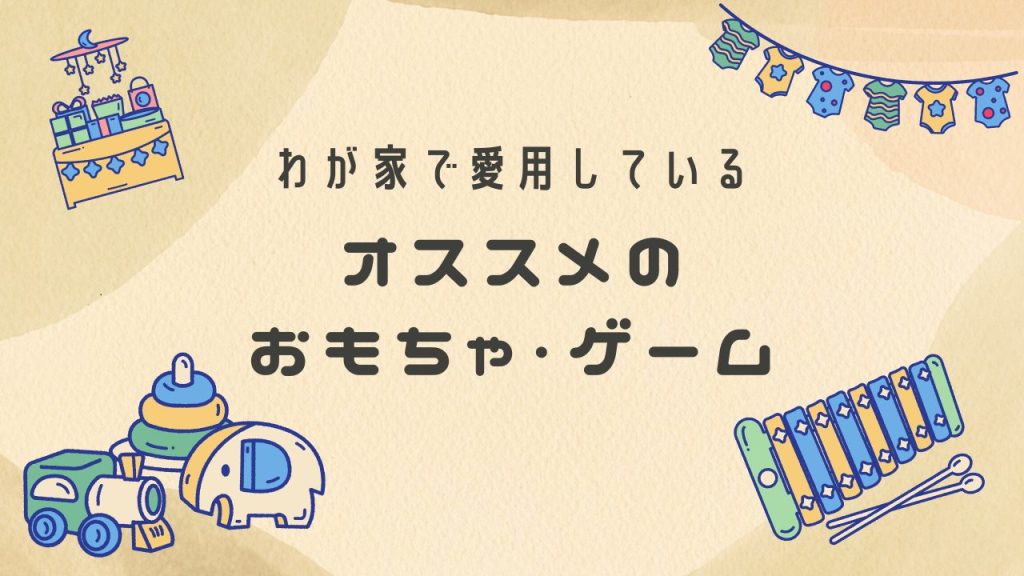少しハードルが高いように思われがちな、「英語のおもちゃ」や「ボードゲーム」。
でも、おうち英語に遊びの要素を取り入れることで、子どもたちと英語との距離をグッと縮めることができるようになります。
そこでこの記事では、
おうち英語で活用しやすい「おもちゃ、ボードゲーム、カードゲーム」のオススメ
を紹介します。

二人娘とおうち英語に取り組む、元世界バックパッカー夫婦。
📚日英絵本2000冊所有、図書館好き
🌎TOEIC900超、海外渡航80カ国超
📖年間読書100冊、育児書150冊読破
🧒🏻👧🏻娘(6y4y)プリインターDWEなし
100以上の事例をリサーチして「おうち英語」スタート。娘二人がバイリンガルに育ったノウハウを発信中!

フラッシュカード

最初に紹介するのは「フラッシュカード」。
ゲーム性を持たせて取り入れている家庭も多いので、おうち英語の必須アイテムとして最初に紹介しておきます。
わが家では↓のカードをかれこれ5年以上使っていますが、子どもにも分かりやすいイラストが特徴で、日常生活で使う基本的な名詞や動詞を覚えることができます。
 たろ
たろわが家では↓↓の3つのセットを使っています。
こちらが動詞のカードがセットになった「Action words」
こちらが名詞のカードがセットになった「Picture words」
こちらが名詞カードの追加版「More Picture words」です。



カードを壁に貼る際は、「音のインプットができていれば、子どもは数回見るだけで覚えてしまう」ので、わが家は数週間で張り替えるようにしています。


カードを貼るのに便利なグッズ



わが家は↓↓の「はってはがせる粘着ゴム」を長年愛用しています。
What am I(ワット・アム・アイ)


英語のものに限らず、わが家ではたくさんのボードゲームを遊んでいますが、おうち英語に特にオススメなのが「What am I」というゲームです。
ルールはすごく簡単で、イラストが書かれたカードを自分に見えないように頭に付けて、相手に質問をすることで、何のカードか当てる、というものです。
制作元:University Games社(アメリカ)
長女のプレイ動画(3〜4歳ごろ)
Guess WHO(ゲス・フー)


こちらも、わが家の子どもたちがよく遊んでいるゲームで「Guess Who」という名前です。
24人のキャラクターの中からお互いに1人を選び、交互に「メガネをかけている?」「帽子をかぶっている?」などイエス/ノーで答えられる質問をして、相手の人物を当てるゲームです。



シンプルながら戦略性が高く、家族や友だちとワイワイ楽しめる定番ゲームです!
制作元:Hasbro社(米国)
Create a Story Cards(ストーリーカード)
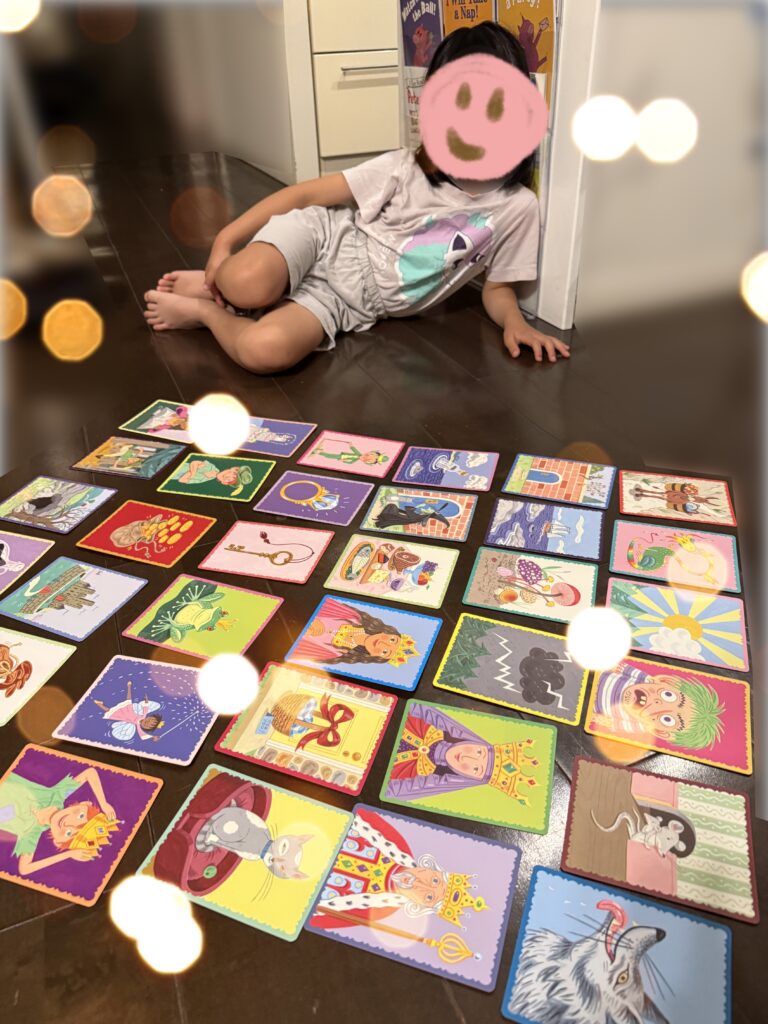
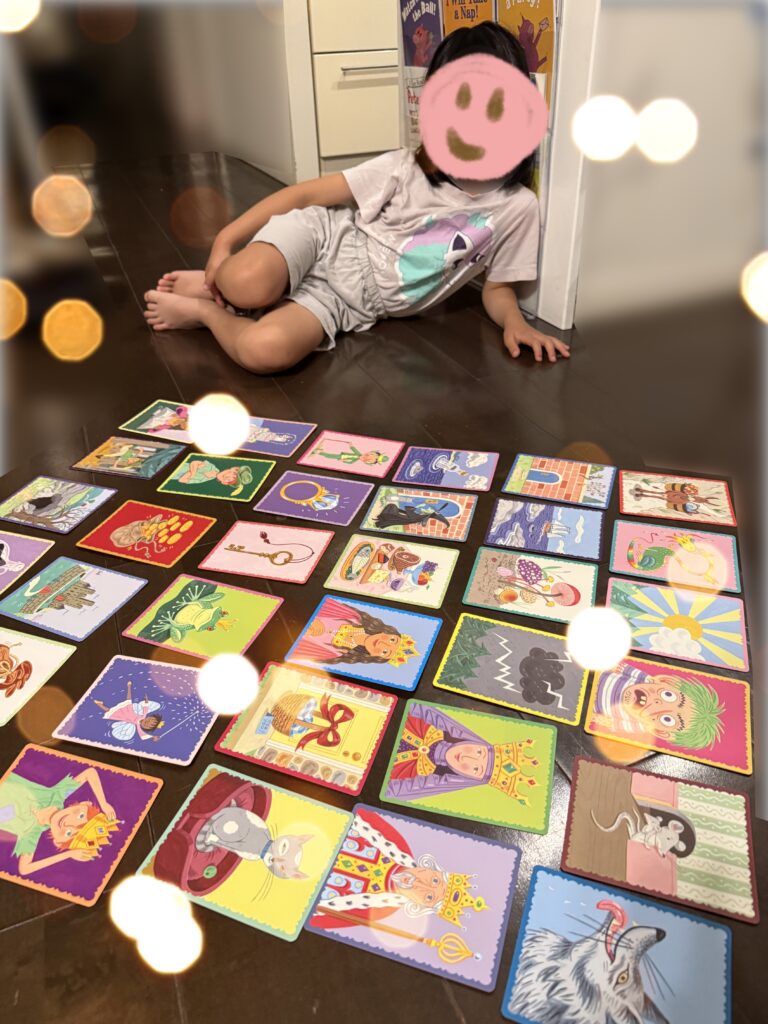
プレイヤーが順番にカードを引き、カードのイラストを元に即興でお話を作って、繋げていくゲームです。
バリエーションが色々あるので、子どもの好みに合わせて選べるのも◎。
- Animal Village:動物たちの村がテーマ
- Mystery in the Forest:森の謎がテーマ
- Volcano Island:火山島の冒険がテーマ
- Fairytale Mix Ups:おとぎ話がテーマ ←わが家が持ってるのはこれ
- A Very Busy Day:パーティーがテーマ
- Magical Forest:魔法の森がテーマ
制作元:eeBoo社(アメリカ)
Story Cubes(ストーリーキューブス)
絵柄サイコロを振って出たイラストを元に自由にお話をつくるゲームです。
わが家はまだ使ったことがありませんが、お出かけや旅行でも使えそうなので、近いうちに導入予定です。
- 対象年齢:6歳以上
- プレイ人数:1人~何人でも
- 所要時間:10~20分
- 内容:9個の立方体サイコロにはそれぞれ異なる絵柄が描かれています。振ったあと、出た絵柄を順番につなげて短い物語を作ります。
制作元:The Creativity Hub社(英国)
おもちゃを購入するタイミングについて


さいごに、おもちゃを購入するタイミングについて、少し書いておこうと思います。
子育てをしていると「このおもちゃを買うのはまだ早いかな?」とか、「すぐに飽きそうだからやめとこうかな?」と考えることは多いと思います。
この点について、しっかりと吟味して良いおもちゃを選ぶというのが大前提ではありますが、
基本的に、おもちゃは気になったタイミングで買ってしまっておいて良い
と私たちは考えています。
敏感期のスパイラル


理由はいくつかありますが、一番大きいのは「子どもは一つのおもちゃをスパイラル(らせん)のように繰り返し遊びながら成長していくもの」だからです。
これは私たちが読んできた150冊以上の育児書と実体験を通して得た知見ですが、子どもが特定のおもちゃに夢中になる時期(=敏感期)は、成長する過程で何度か訪れます。
子どもが夢中になるものは時と共に変わっていきます。まるで移り気があるようです。
(中略)その「らせんの階段」を一周すると、積み木遊びは同じ積み木遊びでも、前よりずっと上手になっている。
下の投稿はわが家の一例ですが、この「ナンバーブロックスのおもちゃ」は、長女が3歳の頃に購入しましたが、その後3回目のブームが到来し、今では次女も一緒に遊んでいます。



英語関連のおもちゃ以外の例は数えきれないほどあって、積み木や楽器、ぬいぐるみなど、数ヶ月から1年の感覚を経て何度も何度も遊んでいます。


おもちゃを長く遊んでもらうコツ


このように、おもちゃは「多少早いと思っても、気になったタイミングで買っておけば」、後に繰り返し遊んでくれるものですが2つほど注意点があります。
一つは、「買おうとしているおもちゃが、何年も使える本物のおもちゃ」かどうかを、しっかり吟味することです。
そして2つ目は、「買ったおもちゃを、常に子どもの目の届くところに置いておく」ことです。
増えるおもちゃとの付き合い方


ですが、2つ目の「子どもの目の届くところにおいておく」は意外と難しいのではないかと思います。
なぜなら、「おもちゃが多すぎて全部出しておくのは無理」「長く使われていないと、親の方が片付けたくなってくる」といった問題が出てくるからです。
私たちも色々と試行錯誤をしながらやってきましたが、これを解決する方法は、一つ目の「本物のおもちゃを選ぶ」。これに尽きるのかなと思います。
良質のおもちゃを少数精鋭で揃えることができれば、片付ける場所に困ることも減りますし、眺めていて心地が良いので親も気になりません。
また、子どもが大きくなっても使えるので、将来買い足すおもちゃの量を最小限にすることができます。
もちろん、子どもが大きくなるにつれて「あのキャラクターのおもちゃが欲しい」と言い始めると思います。
わが家もマンション暮らしで収納に限界があるので、そこは「子どもが自分で選んだおもちゃ専用のスペース」を用意して、そこのおもちゃは子どもが自由に入れ替えられるようにするなど工夫しています。



「良いおもちゃ選びのコツ」については、こちらの3冊がオススメです!