2024年5月15日の早朝。
寝起きでコーヒーを飲みながらGoogleの開発発表をぼんやり見ていた私は、目が覚めるような衝撃を受けました。
Googleが「AIを活用したリアルタイム音声翻訳」を発表したからです。
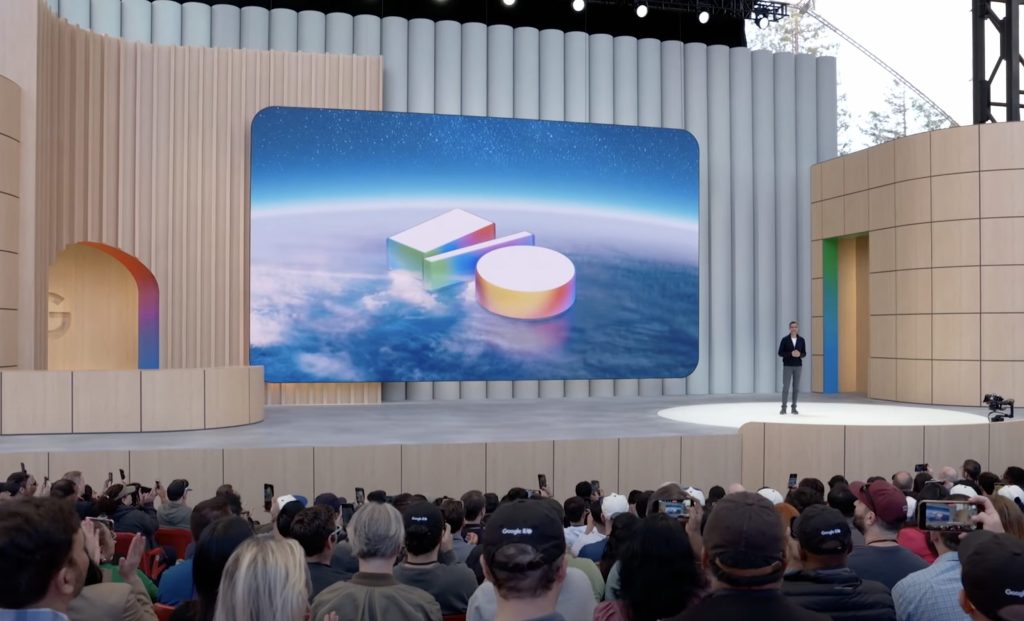
後ほど詳しく紹介しますが、「数年前に想像していた未来が現実になった」と言う実感が湧いてくる内容でした。
そして次に頭に浮かんだのは、「それでもまだ子どもたちは英語を習得する必要があるのか?」と言う問いでした。
これまでに何度も自問自答し、2年前にブログ記事にもしていますが、当時と比べてもAIを取り巻く環境は激変しました。

私たち自身も、生成AIを日常生活で当たり前のように利用するようになり、「英語習得に対する考え」もアップデートされてきました。
そこで、今回の記事では「AIがあるのに、英語を勉強する必要があるの?」という問いについて、現時点での私たちなりの考えを文章に起こしてみることにしました。

二人娘とおうち英語に取り組む、元世界バックパッカー夫婦。
📚日英絵本2000冊所有、図書館好き
🌎TOEIC900超、海外渡航80カ国超
📖年間読書100冊、育児書150冊読破
🧒🏻👧🏻娘(6y4y)プリインターDWEなし
100以上の事例をリサーチして「おうち英語」スタート。娘二人がバイリンガルに育ったノウハウを発信中!

Googleが発表したAI同時通訳の衝撃

© 2025 Google
この季節の恒例となっているGoogleの開発者向けカンファレンスが、今年も開催されました。
例年と比べて革新的な発表が目白押しだったのですが、その中でも特に驚いたのが「AIを用いたリアルタイム翻訳」です。
下の動画を再生すると該当部にジャンプしますが、異なる言語の話者の会話を、人間が同時通訳するのと変わらない速度でアウトプットしています。
自動翻訳サービスは以前からありましたが、それを最も身近なテック企業と言っても過言ではないGoogleが市場に投入することの意味合いは大きいと感じました。
このようなサービスを私たちのような一般の人たちが利用するようになれば、技術革新はさらに加速していくでしょう。
多くの人々にとって、「言葉の壁がなくなる日」が刻一刻と近づいています。
相手の言葉で話せば、心を動かせる

さて、ここで本題に戻ります。
先ほどのGoogleのような事例を見ると、「そんなにすごいAIがあるなら、やっぱり英語を勉強しても意味がなさそう」と感じた方も多いと思います。
私たちも同じように考える事もありますが、様々な視点で考えると次の3つのポイントがあるように思います。
1:相手の心を動かしたい場面では、英語力が強みになる。
2:英語ができる人の希少価値がより高まっていく
3:今の日本の英語教育を受ける必要性が薄れてくる
ここからは、一つずつ具体的に考えをまとめていこうと思います。
1:相手の言語で話せば、心が動く

「AI翻訳」と「自分で外国語を話すこと」を比較してみると、いくつかの違いが見えてきます。
例えば、先ほど紹介した過去の記事にも書いていますが、コミュニケーションにおいて重要な「相手の文化的背景や状況、表情などに合わせて翻訳する」のは人間の方が得意です。
そして、もう一つが「相手の心を動かすこと」です。

ネルソン・マンデラの言葉

*ソウェト:黒人を隔離するために建設された居住地域
南アフリカのアパルトヘイト撤廃、そして同国初の黒人大統領として民主化を導いたネルソン・マンデラ。
私たちが彼の家を訪れた際に知り、印象に残っている言葉に次のようなものがあります。
相手の知っている言語で話しかければ、それは相手の頭に届く。
だが、相手自身の言語で話しかければ、それは相手の心に届く。
ネルソン・マンデラ
まさに、人の心を動かし、世界を変えた人物が「相手の言葉で話す力」の重要性を指摘しています。
他言語話者YouTuberに見る、言葉の力
ここで、一つ分かりやすい例を見てみたいと思います。
上の動画は日本人の他言語話者のKAZUMAさん(13ヶ国語?を話せる)が、世界各地の人たちとビデオチャットするという内容です。
動画を見てもらうと分かりますが、彼が相手の言葉を話した途端に、相手は喜びや驚きの表情を見せます。

似たような経験が私たちもありますが、かつてパタゴニアでテント生活をしながらヒッチハイクしていた時、たどたどしくても現地語でドライバーに話しかけると反応が全く違いました。
スペイン語で挨拶を交わすだけでパッと相手の顔が明るくなり、さらに会話ができると知ると「すごい!すごい!」とみんな興奮気味に話してくれたのを覚えています。
「何に英語を使うのか」が大事になってくる

このように、相手の言葉で話すことができれば、人の心に働きかけることができます。
もちろん「相手の言葉」=「英語」とは限りませんが、英語は世界の共通語として広く使われているので、第1言語でなくても習熟している人が数多くいます。
私自身も、世界各国の企業とのプロジェクトを進める仕事をしていますが、第一言語が英語でないメンバーが多数派でした。

そんな中でも、「英語を使って相手の感情に訴えかけることができた」と感じる場面がたくさんありました。
ですので、「交渉する力」であったり、「リーダーシップをとる力」などは、英語を習得しているかどうかで大きく違ってくると思います。
2:英語ができる人の希少価値がより高くなる

ここまでは、「英語そのものが持つ力」に着目しましたが、ここからは「AI翻訳の進化によって、子どもたちを取り巻く環境がどう変わるのか?」という視点で見てみます。
AI翻訳は今後どうなっていくのか?
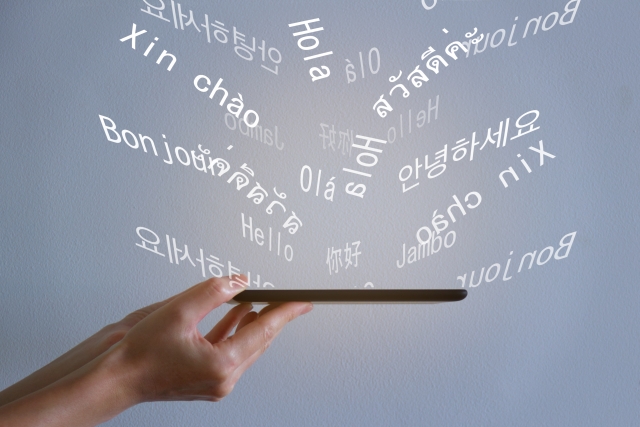
AI翻訳の精度は日々向上しており、TOEIC900点レベルに達しているとの専門家の意見もあります。
一方で、「国際的なビジネスシーンで通用する英会話力を持つ日本人はわずか7%」であると指摘されています。
AI翻訳がウェアラブルになる時代が近い

© 2025 Google
さらに、googleが今回のカンファレンスですでに発表していましたが、AI翻訳がウェアラブルに(メガネやイヤホンなどに内蔵される)なる未来も近いと言われています。
そうなってくると、実用的な英会話はAIに任せる方が効率的であるという考え方が出てきます。
全く勉強していない人に勝てない時代が来る
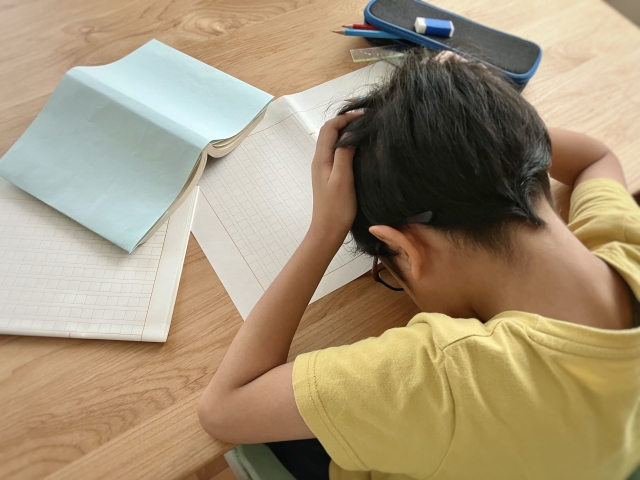
このような状況を考えると、初級や中級レベルの英語を身につけても「AIデバイスを身につけた全く勉強していない人たち」に勝てない時代がきます。
そうなると、英語学習者にとって「中途半端な英語を身につけるぐらいなら、全く勉強しないほうがコスパが良い」と考えるのが合理的になってきます。
すると、英語を「ガチで勉強する」 or 「全く勉強しない」の二極化がより顕著になる未来が見えてきます。

そう聞くと「ますます英語なんて意味ないんじゃないか」と思ってしまいそうですが、別の見方もできます。
「全く英語を勉強しない人たち」が増えるということは、英語ができる人の割合がさらに低くなると言うことです。
つまり、「AIなしで英語を使いこなせる人材」の希少価値が劇的に高くなると考えることができます。
3:今の日本の英語教育を受ける必要性が薄れてくる

さらに、先ほど解説したような現状を考えると、もう一つの疑問が浮かんできます。
それは、「学校の英語の授業を受ける意味はあるのか?」という点です。
日本の大学生の英語レベル

先ほど紹介したように、AIの英語力は既にTOEIC900点レベルに達していると言われています。
一方で、2022年度の公開テストにおける大学生4年生の平均点は 600点前後とされています。
このような現実を見ると、週に数コマの時間を使い、教員の負担も大きい英語の授業の必要性に疑問が出てきます。
AIを前提として柔軟な英語教育が求められる

公教育の英語のカリキュラムは少しずつ変わってきてはいますが、今後は「AIを活用する前提の英語習得」へとシフトさせていく必要があると感じます。
例えば、「生徒たちにAI翻訳機を渡した上で、外国人講師と会話したり、英語で考えをまとめて、発表したりする授業」です。
もちろん英語だけで学校を選ぶわけではありませんが、このような現状を見てしまうと、未就学児の親として悩みの一つになっています。
いま私たち親にできること

以上、私たちが先日のgoogleの発表を見たときに頭に浮かんできた事を、思いつくままにつらつらと文章に起こしてみました。
改めて自分たちの考えを言語化してみて思ったのは、
1:英語を勉強する場合は「海外の大学で学べるレベル」ぐらいを目指さないと、学習する意義がかなり薄れる。
2:公教育の英語をはじめとして、高い英語力が身につかないルートにいる場合は、思い切って英語を切り捨てて他のことに時間を使ったほうが合理的。
3:一方で、これからの時代に英語は必須なので、AIを活用して英語を使いこなすスキルは身につける必要がある。
また、こうしてみていくと「おうち英語で英語の習得を目指す」のは理にかなっていると感じました。
「海外の大学で学べるレベル」を目指すことを考える場合、例えば中学生になってから本腰を入れ始めると、かなりの猛勉強を強いられることになると思います。(子どもが心から楽しんでいればそれで良いと思いますが)

その点「おうち英語」であれば、学習効率の高い幼児期の段階から、子供に大きな負荷をかけずに英語を習得することができます。
ですので、おうち英語で英語の土台を作り、そのまま学習英語レベルに持っていくのは、それなりに理にかなっていると感じました。
今回のテーマは、今の時代を生きるすべての家庭が直面している悩みかと思いますが、みなさんの考えはいかがでしょうか?
公教育の変革の必要性など、日本に住む親が協力して取り組んでいく課題だと思いますので、国内で議論が活発になっていけば良いなと思っています。




